釣り針が刺さったら・・
今すぐ実行できる応急対処がこちらです。
簡単なのはストリングヤンクテクニックで、これは糸を用いた迅速な除去法として知られています。
医療安全面では、釣り針刺入時の感染や破傷風に関する注意点を、公的情報に基づいて確認します。釣り針刺入で起こり得る病名の考え方(刺創など)、受診目安、放置のリスク、救急車を呼ぶか迷うときの相談先、抜けない場合の次の一手まで、釣り針が刺さった処置の全体像を俯瞰します。破傷風になる確率はどの程度かという疑問についても、各機関のガイダンスを参照しながら、予防接種歴と創傷評価の枠組みで整理していきますよ。
- ストリングヤンクテクニックの流れ・コツ・失敗回避
- 他の除去法(ニードルカバー、貫通切断等)との使い分け
- 受診すべき診療科・#7119の活用・救急受診の目安
- 感染と破傷風予防を公的情報に基づいて確認
釣り針が刺さった?応急手順:ストリングヤンクテクニック
- 2025.08.08事件発生
- ストリングヤンクテクニックの手順
- ストリングヤンクテクニックの注意点
- 釣り針 刺さった時の外し方の基礎
- 釣り針が手に刺さった時の抜き方は?
- 抜けない時は
- 救急車の目安
2025.08.08事件発生
日常的に釣りに従事する私。
2025年8月8日、北海道の某漁港で事件発生。
移動中に車内でズレたロッドを直そうとして・・
いつものように釣具を車内のロッドホルダーに乗せて移動してると、投げ竿のいくつかがロッドホルダーからずり落ちて車内に散乱する。
そして、渓流釣りもこよなく愛する私。良い沢があれば即時にロッドを持ち出しものの5分キャストしたい。
そこで、車のロッドホルダーには常にルアーをセットしたロッドを吊るしてある。
車内に散乱した投げ竿を整理していると・・
これより先は体にルアーのフック(針)が刺さった画像があります。苦手な方はブラウザバックを推奨します。
ぐさり。


トレブルフックが返しまでちゃんと刺さります。
これがなかなか抜けない
バーブというものは本当にすごい。
普段は魚の口から簡単にプライヤーで外すが、これが自分の体となると、なぜか話は別。
押したり引っ張ったりするも全く抜けない。
ふと、10年前の記憶が蘇る。
私が釣りを始めた頃、ふと『釣り針が体に刺さったらどうしよう』と考えたことがある。
その際にたどり着いた答えが【ストリングヤングテクニック】である。
10年前の自分に感謝。(この日のためによく準備したなオレ)
ストリングヤンクテクニックの手順
ストリングヤングテクニック(string-yank)は、糸を使って瞬発的にフックを引き抜く応急除去法。専門資料では、浅く刺さった釣り針に対して推奨される選択肢の一つとされ、返し(バーブ)が皮下に軽く掛かった程度であれば高い成功率が期待できると解説されています(参照:MSDマニュアル、AAFP)。以下のステップを順に確認してください。
準備(安全確保と用具)
周囲の安全を確保し、目の保護具があれば装着します。糸は太めで伸びにくい材質(例:PEラインや太い縫合糸)を用意します。30〜40cm程度の頑丈な糸が推奨される(参照:MSDマニュアル)。

ルアーやおもりなど余計な付属物はペンチで外し、針が単体で扱える状態にしておきます。(私の場合、利き手である右腕に刺さったので実はこれが一番大変だった。)

糸を掛ける
針の曲がり(カーブ)部分に糸の輪を通し、抜けた瞬間に飛散しないよう軽く結んで保持します。(この時は面倒くさくて結んでなかった)
飛散は眼の外傷につながるため、専門資料でも飛び出しへの対策が繰り返し強調されています(参照:MSDマニュアル)。

角度固定(最重要)
非利き手でアイ(頭側)を皮膚へ押し付けるように強めに抑え、針の刺入角度を固定する。壁などでもOK。
この時は車のドアで代用した。


この押圧で返しがわずかに後退し、組織との噛み込みが緩む。物理的には、押圧により返し先端と皮下組織の接触が減り、瞬間的な慣性力を与えた際に最小限の組織変位で抜ける状態を作るイメージです。
この時、刺さった針の抜ける方向が自分自身の体になると、引き抜く際にさらに刺さり込むので、しっかりとフックが抜ける進行方向を固定することが重要。
本当に重要なので、もう一度。
フックがしっかり固定されていないとさらにフックがさらに自分自身に刺さり込むので、フックを固定すること。
一気に引く(スナップ)
利き手で糸を刺入方向と正確に逆向きへ、ためらわず瞬発的に引き抜きます。ゆっくり引くと痛みや組織損傷が増えやすく、成功率が下がると解説されています(参照:AAFP)。

これで完了。

抜いた直後がこちら。抜く瞬間の痛みはほぼなし。
少々血が出たくらいで、圧迫すれば5分足らずで止血完了。
これが発生から6時間後。傷跡はほぼ目立たないくらい。
痛みは皆無

抜去後のケア
可能な限り流水と石鹸で洗浄し、清潔な被覆を行います。創の評価に応じて破傷風ワクチンや破傷風免疫グロブリンの適応を確認し、公的ガイダンスに沿って判断することを推奨します(参照:CDC、厚生労働省)。
成功しやすい条件は、浅在であること、返しが皮下に浅く掛かっていること、糸が伸びにくいこと、角度固定が十分なこと、周囲に保護具を備え針の飛散対策を取ること、と解説されています(参照:MSDマニュアル)。
よくある失敗例と教訓:糸をゆっくり引いて痛みが増す/角度固定が甘く皮膚表面をえぐる/ルアーや複数フックが付いたままで引いて飛散する/対象が深在や顔面で自力実施し悪化する――といった事例が報告されています。いずれも角度固定・瞬発・飛散対策・適応判断を徹底することで回避しやすいと解説されています(参照:AAFP、MSDマニュアル)。
ストリングヤンクテクニックの注意点
この手技は適応の見極めが最重要です。専門資料では、眼・顔面・頸部・関節内・腱や神経血管の近傍・深在・多本刺入・ルアー付のまま・大量出血・強い痛みやしびれなどの条件は自力実施を避け、院内での除去(針で覆う方法や貫通切断法、局所麻酔下の処置)へ切り替える判断が推奨されるとされています(参照:MSDマニュアル(深在)、AAFP)。
押圧と牽引方向の精度
押圧が弱い/方向がずれる――これは典型的な失敗パターンです。返しは矢じり構造のため、わずかな方向誤差で皮下組織へ引っかかり損傷が拡大します。皮膚面に向けて強く押さえることで返しの係合を弱め、牽引は刺入と完全に逆向きに、瞬発的に行うことがポイントです(参照:AAFP)。
飛散と二次外傷の予防
抜けた針は弾丸のように跳ぶことがあります。糸を二重にする、結び目で固定する、周囲に人がいれば退避してもらう、目の保護具を使う――など、作業前の安全準備が不可欠です(参照:MSDマニュアル)。
感染・破傷風対策
刺し傷は感染リスクが相対的に高いとされ、洗浄と被覆が基本です。破傷風予防については、ワクチン接種歴・創の性状・汚染の有無でワクチンや破傷風免疫グロブリン(TIG)の適応を評価するとされています(参照:CDC、国立健康危機管理研究機構、厚生労働省)。抗菌薬の日常的な予防投与は推奨されないとの説明もあり、創の状態とリスクで判断する記載があります(参照:MSDマニュアル、CDC)。
ワンポイント:水辺での受傷はビブリオなど水環境由来の菌の関与があり得ます。創汚染が強い、痛み・発赤・腫脹が増強する、熱が出るなどの変化があれば、早期に医療機関で評価を受けるのが安全側とされています(参照:日本創傷外科学会)。
あとは参考に。。時間がない方は読まなくてOKです。
釣り針刺さった?外し方の基礎
外し方の判断は、返し(バーブ)の有無と位置、刺入の深さ、部位(顔面・手指・関節近傍など)、付属物(ルアーやおもり)の有無、出血やしびれの有無といった要素で組み立てるとされています。公的・専門情報では、代表的な除去法としてレトログレード(直線引き抜き)、ストリングヤングテクニック(糸で瞬発的に引く)、針で覆う方法(ニードルカバー法)、貫通切断法(アドバンス&カット)が挙げられ、状況適合性を優先して選択するのが基本と説明されています(参照:AAFP、MSDマニュアル)。
指標としては、返しが皮膚直下に浅く掛かる・眼や関節から離れた軟部組織・出血や強い痛みが軽微・付属物を除去済みなどの条件を満たす場合に、糸を用いるストリング系が選択されやすいとされています。一方、返しが組織に深く噛み込む、角度が悪い、手技で強い抵抗がある等では、18Gの針で返しを覆って同時に抜くニードルカバーや、針先を意図的に貫通させて返しを切断して戻す貫通切断法へ切り替えるのが定石と解説されています(参照:前掲MSD)。
いずれの方法でも、洗浄・被覆・破傷風予防の確認は共通の基本です。専門情報では、易感染性でない限り抗菌薬の予防投与は日常的には推奨されていないという説明があり、症状や汚染の状況に応じて個別判断するとされています(参照:MSDマニュアル)。
判断の目安:①返し無し・極浅在=レトログレード/②浅在・返し浅く係合=ストリングヤング/③返しが障害=ニードルカバー/④中等度〜深在・角度不良=貫通切断――という流れが紹介されています(参照:前掲AAFP・MSD)。
釣り針が手に刺さった時の抜き方は?
手指は腱(けん:筋肉の力を骨に伝える丈夫なひも状組織)、神経、血管が高密度で走行し、少しの方向誤差でも機能障害のリスクがある部位です。専門情報では、痛みが軽度でも〈可動域制限・しびれ・蒼白・拍動性出血〉などがあれば自力処置は避け、院内手技へ移行する判断が推奨されることがあります(参照:MSDマニュアル)。
初期対応は、まず安全確保と固定です。ルアー本体や他のフックが付いていれば必ず外し、針だけを扱える状態にします。流水で周囲の汚れを落とし、アルコール綿があれば手指を清潔にしてから作業に入ります。ねじる・揺さぶる動きは損傷を拡大させるとされ、避けるのが基本です。自力で除去する場合は、ストリングヤンクテクニックの準備としてPEなど伸びにくい糸を30〜40cm用意し、カーブに輪を通して軽く結び、頭側を皮膚へ押し付けて角度を固定し、刺入と正確に逆向きへ瞬発的に引きます。
飛散防止の観点から、目の保護具を用いるか、周囲の人に退避してもらうことが推奨されています(参照:前掲MSD・AAFP)。
抜去後は、石鹸と流水で十分に洗浄し、清潔なガーゼで被覆します。消毒薬は刺激の少ないものを選び、過度な擦過は避けます。破傷風予防は接種歴と創の性状で判断されるとされ、厚生労働省やCDCのガイダンスに沿って、トキソイドワクチン(Td/Tdap)の追加や、必要に応じて破傷風免疫グロブリン(TIG:抗毒素を含む血液由来製剤)を検討する枠組みが示されています(参照:厚生労働省、CDC)。
自力実施を避ける目安:①眼・顔・頸部・陰部・関節近傍/②深く刺さり角度が不明/③出血が持続・拍動性/④強い痛みやしびれ・指が動かしにくい/⑤海や川など汚染が強い環境での受傷――これらは院内評価を優先する条件と説明されています(参照:前掲MSD)。
よくある失敗と教訓:糸が細く伸びて力が逃げる/角度固定が甘く皮膚表面をえぐる/ルアーを付けたまま抜こうとして飛散する/複数本フックを見落とし別の針が刺さる――いずれも糸選び・固定・付属物除去・本数確認で回避しやすいとされています(参照:前掲AAFP・MSD)。
抜けない時は?
ストリングヤングを実施しても、糸が滑る、痛みが急増する、強い抵抗が続くなどのサインがあれば直ちに中止します。専門資料では、ここからの切り替えとして針で覆う方法(ニードルカバー法)または貫通切断法(アドバンス&カット)を選ぶ手順が紹介されています(参照:MSD表)。
ニードルカバー法は、18Gのショートベベル針を刺入部からフック軸に沿って挿入し、返し先端を針の斜面で覆うように位置合わせして、針とフックを同時に後退させて取り出す方法です。利点は、返しによる組織の引っかかりを機械的に遮断できる点で、組織損傷を抑えやすいと説明されています。難点は、局所麻酔や角度合わせの精度が必要で、自宅環境では再現が難しいことです(参照:前掲MSD)。
貫通切断法は、針先を皮膚表面へあえて貫通させ、皮外に露出した返し部分をニッパー等で切断し、残った軸を逆方向へ引き戻す方法です。確実性に優れる反面、出血や疼痛管理、清潔操作が重要で、医療機関での実施が望ましいとする情報があります(参照:前掲MSD)。
判断の流れ(例):ストリングヤングで抵抗が強い→ニードルカバーで返しを覆う→角度が合わない・深い→貫通切断を検討→いずれも不適または高リスク部位→専門医へ搬送。各段階で疼痛・出血・感覚異常があれば停止し、医療判断へ委ねます。
抜去に成功しても、異物残存の可能性(折れた棘、微小片)があれば画像検査が検討されることがあります。金属はX線で映りやすい一方、木片やプラスチックは超音波やCT/MRIのほうが有用なケースがあると説明されています(参照:日本創傷外科学会)。また、海や川での受傷では水環境由来の菌が関与する可能性があるため、発赤・腫脹・疼痛増強・発熱などの変化があれば早期受診が安全側とされています。
よくある失敗と教訓:抵抗があるのに反復牽引して創を拡大/工具が不十分で切断部が飛散/不適切な消毒で皮膚刺激を増やす――などが挙げられます。対策として、一度の判断で切り替える勇気、清潔・安全準備、術後の観察を徹底することが挙げられています(参照:前掲MSD)。
救急車の目安
受傷時に救急車を呼ぶか迷う場面は少なくありません。日本では、総務省消防庁の救急安心センター事業(#7119)が各地域で整備され、医師・看護師等による電話相談で緊急度判定を受け、必要に応じて119へ接続される仕組みが案内されています(参照:総務省消防庁、東京消防庁)。
救急要請の優先度が高いとされる状況としては、眼球・口腔・咽頭への刺入、大量出血や圧迫で止まらない出血、意識障害・けいれん・ショック疑い(冷汗、顔面蒼白、脈が弱い)、呼吸困難やぜいぜいする呼吸、重度のアレルギー反応(全身のじんましん、唇や舌の腫れ)、関節内や腱・神経の明らかな障害が疑われる場合などが挙げられています(参照:京都府、前掲消防庁)。
| 状況 | 推奨行動 | 備考 |
|---|---|---|
| 眼・口腔・咽頭への刺入 | 119番通報または#7119経由 | 自力処置を避け、体位を安定 |
| 止血困難な出血 | 強圧迫しながら119番 | 清潔布で直接圧迫、患部挙上 |
| 意識障害・呼吸困難 | 直ちに119番 | 可能ならバイタル観察と保温 |
| 関節内・腱神経障害疑い | #7119で指示を確認 | 固定し動かさない |
| 軽度〜中等度の表在刺入 | 自己対処後に外来受診 | 破傷風予防と感染徴候の観察 |
救急要請の可否は時間帯・交通事情・受傷者の年齢や基礎疾患も影響するとされます。判断に迷う場合は、#7119で助言を受けること、近隣の救急当番医の情報を自治体サイトで確認することが推奨されています(参照:前掲消防庁)。なお、抜去を急ぐよりも安全確保と状態評価が優先という点は、多くの公的資料で共通して強調されています。
釣り針が刺さったら?感染のリスク
刺し傷は入口が小さく見えても、内部は深く狭いトンネル状になりやすく、汚染物や微小な異物が残ると酸素が届きにくい環境が生まれ、細菌が増殖しやすいと解説されています。
医療系の解説では、刺し傷の基本は十分な洗浄・異物の確認・清潔な被覆・観察であり、易感染性(糖尿病、免疫抑制など)でない限り、抗菌薬を日常的に予防投与することは推奨されないとされています。これは抗菌薬の不必要な使用で副作用や耐性化の問題が生じる懸念があるためで、むしろ創の状態の変化を見逃さないことが重要と説明されています。
症状としては、疼痛の増強、発赤の拡大、熱感、腫脹、膿性滲出、悪寒や発熱が典型で、24〜48時間の経過観察中に悪化する場合は受診を急ぐのが安全側とされています。浅い刺入でも、土壌や海水などで汚染されていると感染リスクは上昇し、海水環境ではビブリオ属などの関与が指摘されるため、受傷背景の聴取(川・海・プール・養殖場など)も判断材料になります。金属フックの破片が残存する可能性がある場合はX線が有用とされる一方、木片やプラスチックなどは超音波やCT/MRIが選択肢となり、画像検査を組み合わせて異物残存を探索するアプローチが紹介されています。
創面は石鹸と流水で優しく洗い、アルコールや刺激の強い薬剤で擦り込むような処置は避けるのが無難とされています。これらは創の保護機能を損ね、かえって治癒遷延や刺激性皮膚炎を起こすリスクがあるためです。
創の縫合は刺し傷においては原則行わず、感染の兆候が乏しく十分な洗浄ができていても、一次閉鎖を急がずに開放創で管理する方針が提示されることもあります。負担の少ない鎮痛(アセトアミノフェンなど)や患部の安静・挙上も自宅ケアの柱です。
専門情報では、腱・神経・血管損傷が疑われる所見(可動域低下、しびれや感覚鈍麻、拍動性出血、蒼白)は合併症のサインとして重要度が高く、救急または専門外来での評価が望ましいとされています。こうした体系だった考え方を押さえると、「どこまで自分で様子を見るか」と「いつ医療につなぐか」の線引きが明確になります。
受診の判断に役立つチェック:①痛み・発赤・腫れが時間とともに強くなる/②膿や悪臭が出る/③発熱・悪寒・全身倦怠/④指が動きにくい、感覚が鈍い/⑤水辺での受傷や泥汚染が強い――一つでも該当すれば早期受診が安全側です。専門団体の資料では、異物残存の疑いがある時は画像検査の併用が推奨されています。
破傷風になる?
破傷風は破傷風菌(Clostridium tetani)の産生する神経毒素で発症する疾患で、刺し傷・咬み傷・汚染創などの低酸素環境で芽胞が発芽しやすいと説明されています。
公的な指針では、予防の基本はワクチン(トキソイド)による免疫と創傷管理で、受傷時には「創の性状(清潔か汚染か、深さ、壊死組織の有無)」と「本人のワクチン接種歴(最終接種からの年数、完了の有無)」を組み合わせ、追加接種や破傷風免疫グロブリン(TIG)の適応を判断する枠組みが採られています。
たとえば、米CDCの臨床ガイダンスでは、汚染が疑われる創や深い刺し傷では、最終接種からの年数が経過している場合に追加のトキソイド接種が示され、既往接種が不十分な場合や重度汚染ではTIGの併用が検討されると記載されています。
また、抗菌薬は破傷風の予防目的では推奨されないとされ、洗浄・デブリドマンとワクチン/TIGが柱であることが明確に示されています。日本の公的情報でも、定期接種制度や成人での追加接種の重要性が周知されており、受傷後の対応では医療機関で接種歴の確認を行い、必要に応じてトキソイドやTIGを用いるとされています。
なお、一般に問われる「破傷風になる確率」については、地域のワクチン接種率、個人の免疫状態、創の汚染度など多数の条件に依存するため一律の数値で説明することは難しいとされます。公的資料は、統計値の単純比較よりも、接種歴に応じた予防に重心を置く実務的な方針を示しています。
日常的な備えとしては、母子健康手帳や接種記録の把握、10年ごとのトキソイド追加(各国推奨のスケジュールに準拠)を意識し、受傷時は医療機関で確認するのが最短経路です。
用語解説:Td/Tdap=成人向け破傷風・ジフテリア(+百日せき)トキソイドワクチン。TIG=破傷風免疫グロブリン(既にできた毒素ではなく、毒素を中和する抗体を含む製剤)。トキソイド(無毒化毒素)で能動免疫を底上げし、必要時はTIGで受傷直後に一時的な受動免疫を補う考え方がガイドラインで示されています。
病院の選び方
受診先の基本は、外科・整形外科・形成外科・救急外来です。
平日日中の表在的な創で全身状態が安定している場合は地域の外科系クリニックでも評価可能ですが、夜間・休日・小児・基礎疾患のある方・強い症状では救急外来が無難です。
部位・症状別にみると、眼や顔面、関節内、腱・神経・血管損傷が疑われるときは専門性の高い病院が望ましく、深在例や「ストリングヤングで強い抵抗があった」ケースも院内手技(針で覆う方法、貫通切断など)に切り替える適応と説明されています。
迷うときは日本各地で整備が進む#7119(救急安心センター)が24時間対応で、看護師や医師などが緊急度を判定し、必要時には119へ接続される運用が案内されています。東京消防庁の紹介ページでは、サービスの目的や活用例が具体的に記され、相談件数や必要接続の割合など運用状況も公表されています。
実務的な使い方としては、(1)今すぐ救急車か自己搬送かの判断、(2)受診時期と診療科の助言、(3)応急のセルフケアの確認、の3点で活用するとスムーズです。なお、受診前準備として、受傷状況(場所・汚染・道具)・接種歴・既往症・常用薬(抗凝固薬など)をメモしておくと、診療が迅速化します。
| 症状・状況 | 推奨診療科 | 備考 |
|---|---|---|
| 表在の刺入で全身安定 | 外科・整形外科 | 異物疑いでは画像で確認 |
| 顔面・眼・関節近傍 | 救急外来→必要に応じ形成・眼科 | 自力除去は避ける |
| 指の運動障害・しびれ | 整形外科(手外科)・救急 | 腱・神経損傷評価 |
| 強い汚染・海水での受傷 | 救急・外科 | 感染評価と破傷風予防 |
| ストリングで抵抗が強い | 救急・外科・形成外科 | ニードルカバー等の院内手技へ |
刺さったまま放置は危険
放置の最大の問題は、見た目の軽さと内部の重さが一致しないことです。
刺し傷は入口が小さく閉じやすいのに対し、内部には汚染や微小異物、壊死組織が残存しやすく、感染が遅れて顕在化することがあります。
専門情報では、刺し傷の合併症として創感染・蜂窩織炎・膿瘍形成・慢性の肉芽腫形成などが挙げられ、特に返しつきの釣り針は組織に係留し、動かすたびに微小損傷と出血を繰り返すため、痛みが軽いうちに正しい手順で除去するのが理にかなうと説明されています。
海や川、泥での受傷は環境由来の菌が多様で、初期は軽度でも悪化のスピードが早いことがあり、赤みの広がり・ズキズキする痛み・熱感が続く場合は早期受診が安全です。
また、異物が残ると慢性炎症や肉芽が形成され、硬いしこりや色素沈着の原因になることがあり、審美面・機能面の問題へ波及します。破傷風についても、接種歴が不明なまま経過観察だけを続けると予防の機会を逸するリスクがあります。
したがって、「放置して様子を見る」のは例外的な状況(ごく浅い刺入で清潔、症状が乏しく、注意深い観察ができる場合)にとどめ、基本は初期洗浄・被覆・観察・必要時受診・接種歴確認の流れを踏むことが推奨されています。専門資料は、刺し傷では縫合を急がず、感染徴候がないかの評価と異物の有無の確認を優先する方針を示しています。
よくある失敗と教訓:①痛みが弱いからと放置→翌日以降に腫脹・発赤が増強/②消毒薬の強擦で皮膚刺激が悪化/③破傷風の接種歴確認を後回し――どれも初期の「洗浄・被覆・観察・予防確認」を徹底すれば回避しやすいとされています。
ストリングヤンクテクニックまとめ:釣り針(フック)が刺さったら?
- ストリングヤンクテクニックは浅在例で選択されやすい
- 糸は太めで伸びにくい材質を選ぶ
- 頭側を皮膚に押し当て角度を固定する
- 刺入と正確に逆向きへ瞬発的に引く
- 抵抗や強い痛みがあれば中止する
- 顔面や眼・関節近傍・深在は自力で行わない
- 抜去後は洗浄と清潔な被覆を維持する
- 抗菌薬の予防投与は原則常用しないという情報がある
- 破傷風は接種歴と創の性状で予防を判断する
- 受診先は外科系・救急、迷えば#7119を活用する
- 異物残存が疑わしければ画像で確認する
- 水辺での受傷は早期受診を意識する
- 放置は感染や肉芽形成のリスクがある
- 創の変化(痛み・赤み・腫れ・熱)を観察する
- 迷ったら安全側で医療機関に相談する
このルアーが釣れるんですよ・・痛かったですが笑
参考リンク・公的情報(確認用)
- MSDマニュアル|浅く刺さった釣り針の抜去
- MSDマニュアル|深く刺さった釣り針の抜去
- MSDマニュアル|釣り針の抜去(針で覆う方法)表
- AAFP|Fishhook Removal(総説)
- CDC|Tetanus Clinical Guidance
- 国立健康危機管理研究機構|破傷風 基礎情報
- 破傷風 抗体保有状況(サーベイランス)
- 厚生労働省|破傷風情報・接種案内
- 日本創傷外科学会|刺し傷の基礎知識
- 総務省消防庁|救急安心センター事業(#7119)
- 東京消防庁|救急相談センターの案内
- 京都府|救急安心センターきょうと(#7119)
上記リンクは2025年時点で公開されている公的・専門情報への参照です。各地域の運用や連絡先は告知なく更新されるため、最新情報は必ずリンク先でご確認ください。
この記事でご紹介した方法はあくまで応急的な対応です。最も大切なのは、「フックが体に刺さらない管理」「適切な医療機関の受診」です。あくまでもご参考程度に。
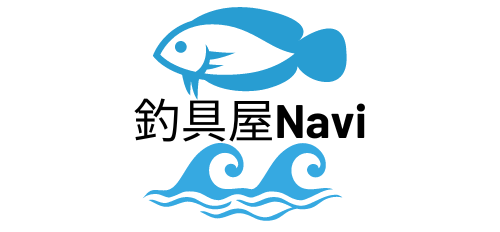

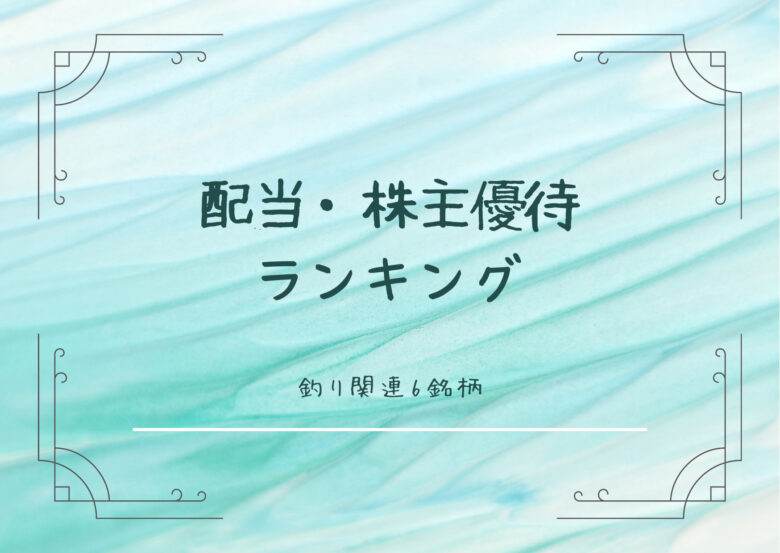


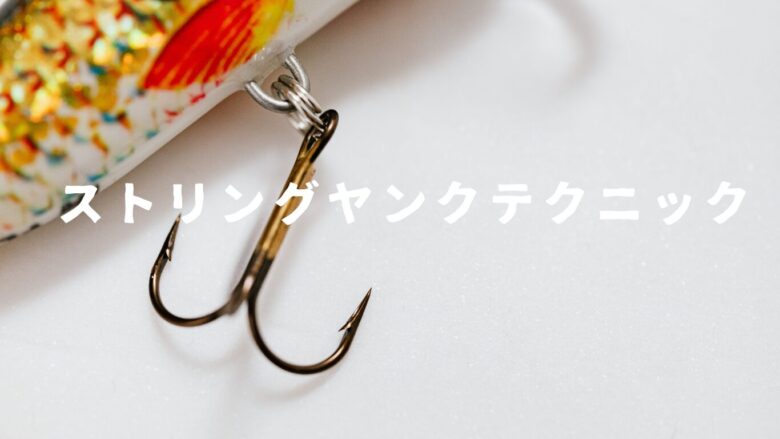


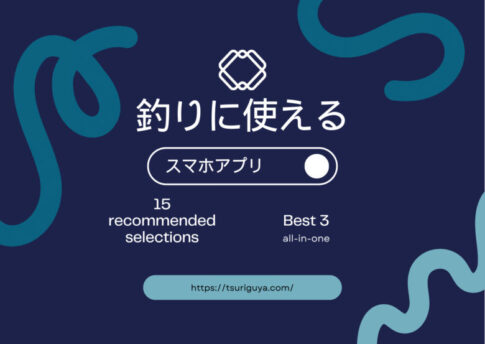
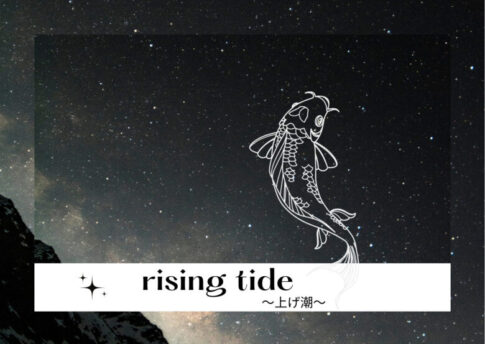


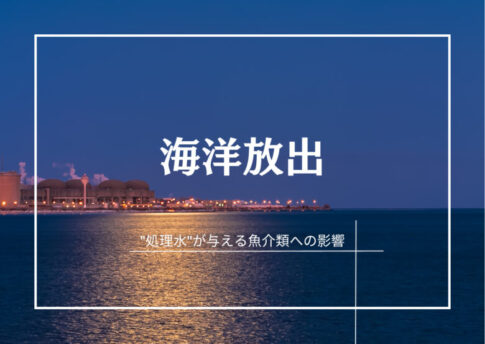
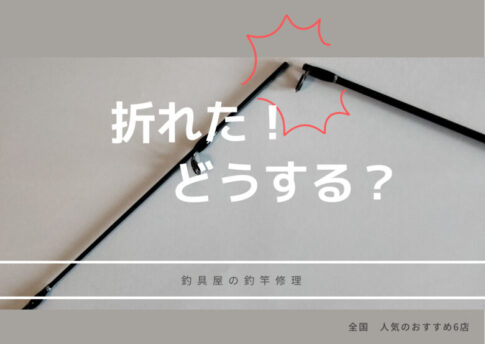






コメントを残す